「頑張っているのに痩せない…」
そんなときに見直したいのが、ダイエットの根本ルールです。
人体が痩せる仕組みの原則は消費カロリーが摂取カロリーを上回っている状態にある時です。
このシンプルな原則こそ、体脂肪を落とすための土台です。
今回は、戦略的に痩せるために「どれくらい食べて・どれくらい動けばいいのか」が見えてくるように、カロリーの考え方を丁寧に解説していきます。
体重が減る仕組みは「赤字を作る」こと
最初に伝えた通り体重を減らすには、摂取カロリー(食べたエネルギー)より、消費カロリー(使ったエネルギー)を多くする必要があります。
これは「エネルギー収支の赤字」を作るという考え方です。
- カロリー収支がプラス(摂取カロリー>消費カロリー) → 体脂肪が増える
- カロリー収支がマイナス(摂取カロリー<消費カロリー) → 体脂肪が減る
つまり、「痩せる=赤字」ということ。この構図が成り立っていないと、いくら運動しても体重は落ちません。
1日に必要な摂取カロリーの目安
まず、目安として知っておきたいのは、1日に必要なカロリー量。
これは年齢・性別・身長・体重・活動量によって変わりますが、厚生労働省の基準では以下のようになっています。
- 成人男性(18~64歳)
→ 約2,200〜2,800kcal/日 - 成人女性(18~64歳)
→ 約1,400〜2,000kcal/日
あくまで目安なので、個人差があります。実際に自分が「どれくらい食べているか」を一度アプリなどで記録してみると現状がつかめます。
消費カロリーを構成する3つの要素
1日に使われるエネルギーは、以下の3つに分かれます。
- 基礎代謝:生命を維持するために最低限必要なエネルギー(約60%)
- 活動代謝(身体活動による消費):日常生活や運動による消費(約30%)
- 食事誘発性熱産生(DIT):食事を消化・吸収する際のエネルギー(約10%)
中でも特に大きな差が出るのが「活動代謝」です。
活動レベル別|1日の消費カロリー目安
活動代謝は、日常の動きや運動量によって大きく変わります。
下記のように「活動レベル」に応じて係数(PAL)を使うことで、総消費カロリー(TDEE)が計算できます。
| 活動レベル | 例 | 係数(PAL) |
|---|---|---|
| 低い(1.5) | デスクワーク中心、運動なし | 1.5 |
| 普通(1.75) | 立ち仕事、週1〜2回の運動 | 1.75 |
| 高い(2.0) | 肉体労働・日常的に運動習慣あり | 2.0 |
TDEE(総消費カロリー)=基礎代謝 × 活動係数
たとえば、基礎代謝が1,500kcalの人で、活動レベルが「普通」の場合:
- 1,500 × 1.75 = 約2,625kcal
この2,625kcalが、1日に使っているカロリーの目安です。
ダイエットを始めるときは、ここから300〜500kcal程度引くことで無理のない減量ペース(週0.5kg程度)になります。
つまり、「消費カロリー」を上げるには筋肉を増やしたり、日常的に体を動かすことが有効です。
ちなみに基礎代謝は身長、体重、年齢、性別で変わってきます。基礎代謝は以下から算出可能です。

摂取カロリーの管理はアプリを活用
「カロリーなんて計算できない」と思うかもしれませんが、
最近ではMyFitnessPal(筆者も愛用しています)やあすけんなど食べたものを記録するアプリが充実しています。
✔ 最初の3日間だけでも良いので試しに記録してみる
✔ 自分が何をどれだけ食べているかを「見える化」する
この一歩が、無意識の間食や過食に気づくきっかけになります。
まとめ|ダイエットは戦略がすべて
✔ ダイエットは「摂取<消費」の赤字状態を作ること
✔ 消費カロリーは基礎代謝×活動係数で計算できる。基礎代謝はこちらから算出できます。
✔ 無理なく続けるためには1日の摂取カロリーからマイナス300〜500kcalの赤字が理想
✔ 記録アプリを使うことで、摂取カロリーも把握しやすくなる
数字にこだわりすぎる必要はありませんが、目安を知ることは成功率を上げる近道です。
Reset+では、今後も“続けられるダイエット”や“習慣化のコツ”などを発信していきます。
ぜひ、自分に合ったやり方を見つけて、無理のない戦略で痩せていきましょう。

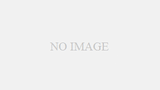
コメント