「筋トレをしてるのに、なかなか痩せない」「体重は落ちないし、見た目も変わらない」
そんな悩みを感じたことはありませんか?
実は、ダイエットは運動だけでは成功しません。カギになるのは“食事管理”。
この記事では、運動してるのに痩せない理由と、結果につながる食事の見直しポイントを解説します。
運動しても痩せないのはなぜ?
沢山運動してるのに痩せないのはなぜでしょう。理由はシンプルです。
体は「食べたものでできている」
今の体型は普段の食事によって作られた結果です。
結論、体型や体重は、運動よりも食生活の影響が大きいです。
筋トレをすれば筋肉は刺激されますが、それ以上に食事の内容や量が乱れていれば痩せるどころか逆に太ります。
脂肪が減らない=カロリー収支がマイナスになっていない
脂肪が減る仕組みはシンプルで、「消費カロリーが摂取カロリーを上回る」必要があります。
つまり、筋トレで運動していても、摂取カロリーが多ければ痩せないのは当然なんです。
関連記事:
痩せるための基本は「消費カロリー>摂取カロリー」
ダイエットの本質はエネルギーの収支バランスにあります。つまり消費カロリーと摂取カロリーの関係を意識することです。
体脂肪は余った摂取エネルギーが使われず貯金されたものです。減らすには、1日の消費カロリー>摂取カロリーを徹底することが最優先です。
筋トレしても、食べ過ぎてたら痩せません
筋トレ1回で消費するカロリーは約150~300kcalと意外と少ないです。
それなのにプロテインや間食を無意識に摂っていれば、逆にオーバーカロリーになっている可能性があります。
食事管理で意識すべき3つのポイント
ここで痩せるための食事管理で意識したい3つのポイントを紹介します。
① PFCバランスを整える
P(タンパク質)F(脂質)C(炭水化物)のバランスを整えると、筋肉を維持しながら脂肪を減らすことができます。
以下を意識して毎日の食事内容を見直してみましょう。
✔ タンパク質:体重×1.6g~2gを目安に
✔ 脂質:全体の20~25%程度
✔ 炭水化物:体調や活動量に応じて調整
例えば、60kgの男性が一日1,800kcalで食事をするとなった場合:
- タンパク質:96g(体重×1.6g)
- 脂質:50g(全体の25%程度)
- 炭水化物:約240g(タンパク質と脂質のカロリーを引いて計算)
といった感じになります。
② 食べるタイミングに注意する
夜遅くの食事や空腹時間が長すぎると、脂肪がつきやすくなります。
特に夜は脂肪をため込みやすい時間帯。夕食は就寝2〜3時間前までに済ませましょう。
逆に筋トレ後は食べた食事の栄養素を回復に回すので、もし夜食べる際は筋トレ後がおすすめです。
③ 継続できるルールを決める
完璧な食事を目指すよりも、「夜だけ糖質を控える」「毎日プロテインを飲む」など継続できる1ルールを決めるのがコツです。
筆者は減量時「夜の炭水化物は130gに抑える」から始まり「昼は鶏肉、夜は魚(鯖缶)」といった感じで、継続しやすいルールを徐々に増やしていきました。
まず見直すべきは「間食・飲み物・調味料」
実は食事以外の箇所を見直すことで摂取カロリーを抑えることが出来ます。
意外とカロリーを摂っている“落とし穴”
・砂糖入りのカフェラテ
・マヨネーズやドレッシング
・お菓子・スナック・惣菜パン
これらは習慣的に摂取してしまいがち。一見小さなカロリーの積み重ねが体型に影響します。
カフェラテはブラックコーヒーかお茶、マヨネーズやドレッシングは青じそドレッシングなど脂質が無いものを選ぶ。お菓子・菓子パンは確実に控えましょう。
もしお菓子や菓子パンを控えることにストレスを感じる方は置き換え食を活用してストレスなく食習慣を改善できます。
たとえばスナックはプロテインバー。菓子パンはベースブレッドなどといった感じです。
初心者あるある(Q&A形式)
Q1. 食事を意識するとストレスで続かない…
→ 完璧じゃなくて大丈夫。まずは「夜の炭水化物を控える」など1つのルールから始めてみてください。
Q2. プロテインは飲むべき?
→ タンパク質が足りていないなら飲むのがおすすめ。食事で摂れれば無理に飲む必要はありません。
Q3. 食べてないのに痩せないんだけど?
→ “食べてないつもり”が盲点。調味料や飲み物を見直してみましょう。
まとめ
筋トレを頑張っているのに痩せないと感じたら、それは食事管理のサインです。
カロリー収支、PFCバランス、食事のタイミングといった基本を見直すだけでも、体は確実に変わり始めます。
✔ 食べすぎを見直す → まずは成分表チェック。カロリー、タンパク質、脂質、炭水化物の量を
✔ PFCバランス → タンパク質は意識して多めに
✔ ストレスをためずに続けられる方法を選ぶ
Reset+では、ダイエット初心者でも続けられる「現実的な工夫」を紹介しています。
次はぜひ、食事をラクに整えるアイテムも取り入れてみてください。

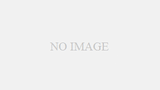




コメント